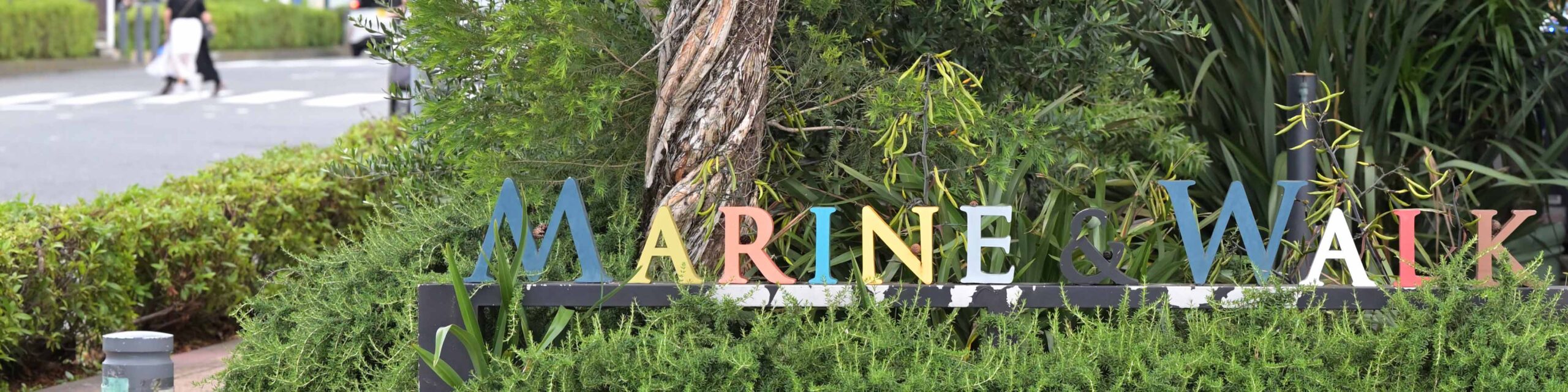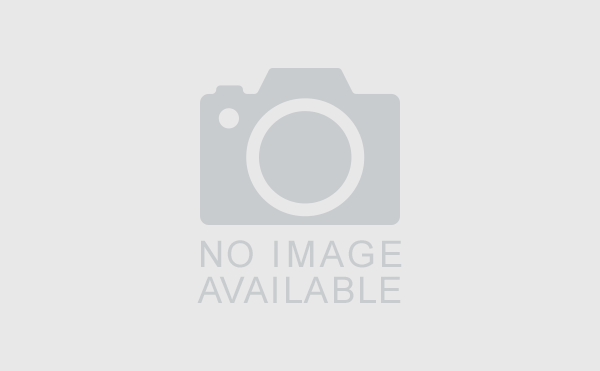・『~技術的に低く日常的なものを撮っていて、構成やアングル、色彩にも既視感が拭えないような写真、とりあえずスナップ写真と呼んでおくが、その写真が写真集になり、展示会で展示されたとき~、見る人の誰もが抱く疑問は、「私が撮った写真とどう違うのか」ここに写真批評の困難は尽きている。~有名な誰それの写真と私の撮る写真と、どこがどう違うのか分からない~』
・これは美術手帖2002年04月号に掲載されている美術評論家しみずみのる氏の論文の抜粋です。さらに氏は「~写真表現の内実は見る者と作品のあいだに生じる交流から事後的に生じるしかなくなる~」といい、以下1990年代以降の現代写真とティルマンスについて論じています。
・昨年の神奈川県サロン展で、竹沢うるま氏は「竹沢うるまが、今この時に審査して選んだ結果です。選者が変われば、時が変われば審査結果は変わる」「写真は作者と見る人の感性の交流だ」と話していました。
・日頃、私が写真活動をしていて感じることは、写真作品の価値を判断する要素はとても多くて、その要素の中の何を重視した見方をするかで作品価値は大きく変わります。見方は人が変われば変わるのでまさに混沌です。
・光画塾では、作者が何を見て、何と向き合い、何を感じたのか。それをどう表現して伝えるかをスタートラインにしています。人によって受け止め方が異なるので、全員の目で見て、全員のディスカッションで作品と感性の交流をして次の作品作りに活かすワークショップを続けています。おかげさまで、写真表現をおおいに楽しんで1年半が経ち、今年は写真展を開催しました。